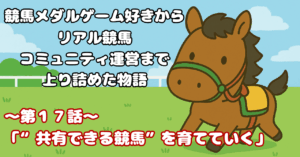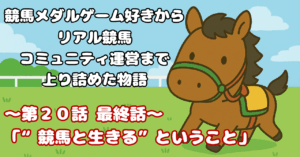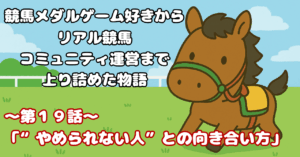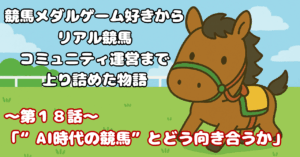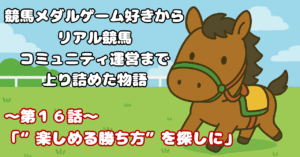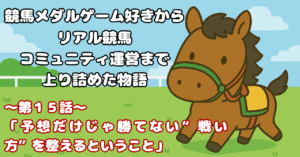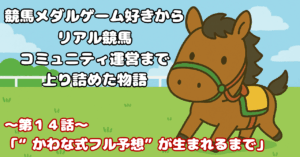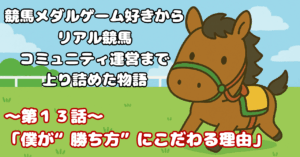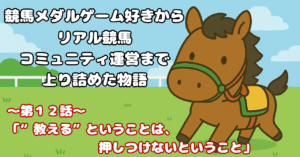第17話 「“共有できる競馬”を育てていく」

競馬ストーリー連載|第17話
「“共有できる競馬”を育てていく」
――一人じゃない。勝ち負けを超えて繋がる競馬の話
▼ 僕は「当てる力」だけじゃなく、「伝える力」も磨きたかった。
予想を組み立てる力だけでは、競馬は伝わらない。
その背景にある思考や、展開の読み、買い方の理由まで、
一つずつ丁寧に「言葉にする」ことが、僕にとっては大事だった。
「なんでこの馬が本命なんですか?」
「なぜこの買い方にしたんですか?」
そう聞かれたときに、迷わず“言葉で返せる力”があって初めて、
予想が“共有できるもの”になると思ってる。
▼ 共有できる競馬は、孤独をなくす。
一人で予想して、一人で外れて、悩んで、落ち込んで。
それも競馬のリアルだけど──
「こういう展開を読んでいたよね」
「この馬、惜しかったですよね」
「お互い狙いは間違ってなかった!」
そんな会話があるだけで、
外れたレースも“学び”に変わるし、競馬がちゃんと前に進む。
僕がマンツーマンで会員様とミーティングをする理由は、そこにある。
▼ ミーティングの内容は、競馬の話だけじゃない。
もちろん、競馬の反省会や、
自分が知っている馬券テクニックのシェア、
コンピデータの検証法なんかもやっている。
でも実際には、
ただの雑談で終わる回も、全体の3割くらいある。
「月に1回、誰かと競馬を語る」
それだけでも、心がスッと軽くなって
競馬がもっと好きになる。
そんな会員様も、確実にいる。
▼ そこに気づいてから、僕の中で考えが広がった。
競馬って、当てるだけじゃなくて
「語れること」そのものが価値になるんだって。
だから、馬券的中率アップの会では、
会員様同士の交流会も大賛成。
競馬をきっかけに仕事の話になったり、
新しいプロジェクトが生まれても全然いい。
競馬というフィルターを通して、
人と人が繋がることが、僕にとっての理想。
▼ 勝ちよりも「わかり合える瞬間」が嬉しい。
- 「先行馬拾えてましたよね」
- 「展開、ズバリでした」
- 「でも3着ヌケはしょうがないです…」
そうやってお互いに予想を照らし合わせて、
納得できる結果も、悔しい結果も共有する。
これは、ただの“予想の答え合わせ”じゃない。
「競馬力そのもの」を一緒に育てている感覚なんだ。
▼ 予想を通じて、関係性も育っていく。
- 名前だけじゃなく、“中身”が見える会話
- 競馬の好みやスタイルも、お互いに理解できる
- 少しずつ、でも確実に築かれていく信頼感
僕は、この空気感が大好きだ。
▼ 競馬は、本来“応援するもの”だ。
僕らは「馬が頑張る姿」を見て熱くなる。
「騎手の勝負根性」にしびれる。
「陣営の仕上げ」に感動する。
その熱を、誰かと分かち合えたら──
きっと競馬はもっと、心が動く娯楽になる。
▼ 馬券は孤独だけど、競馬は一人じゃなくてもいい。
「勝った」「負けた」だけじゃなく、
「共有できた」「通じ合えた」からこそ、また頑張れる。
僕は、そういう競馬を育てていきたい。
▶️ 次回予告:「“AI時代の競馬”とどう向き合うか」
ChatGPTやデータ分析…
今、競馬はAIという“新しい相棒”と出会っている。
でも、便利さの裏には“危うさ”もある。
僕がAIをどう捉え、どう伝えているか──そのリアルを語ります。